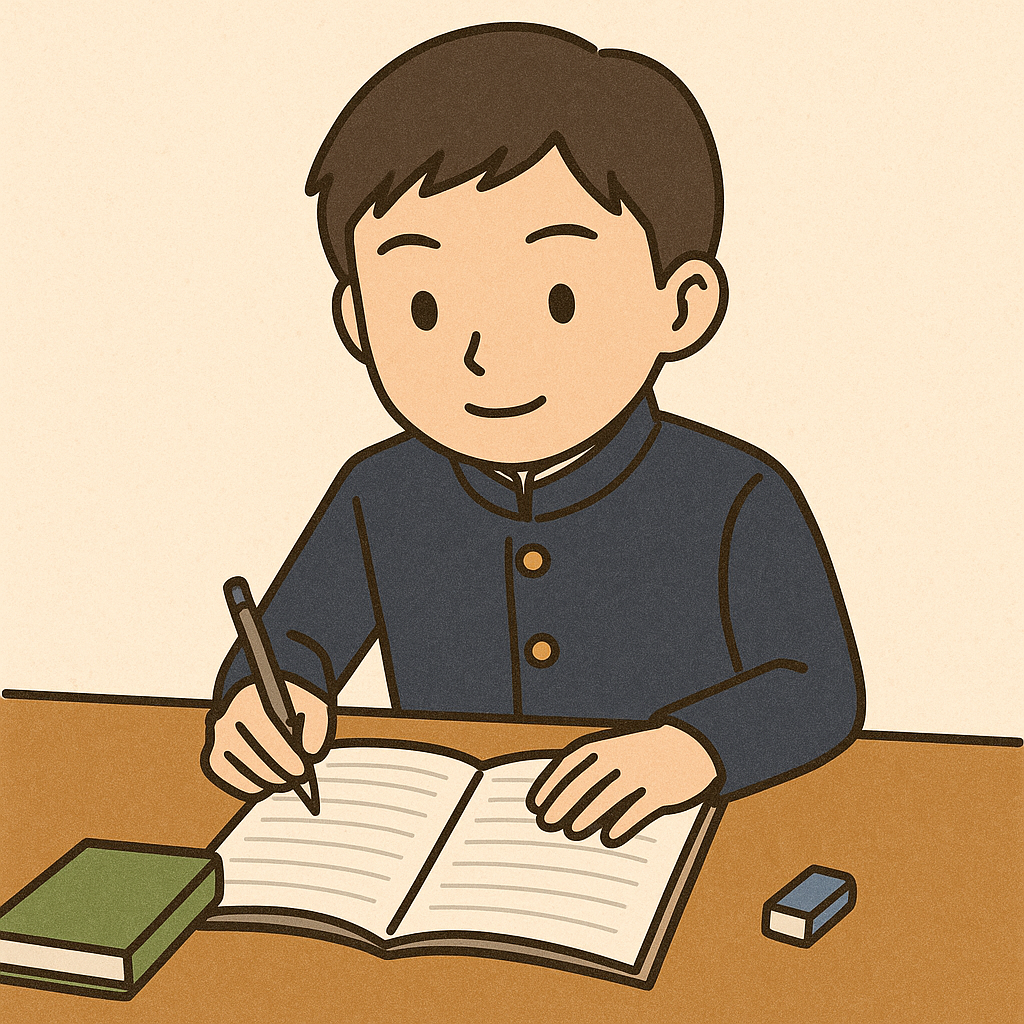口うるさく言うより、あたたかく見守る
「やる気の芽」を守るために
子どもが勉強を続けるには、安全で心地よい空気が欠かせません。
🙅口うるさく言うのは、やる気の芽を摘んでしまう大きな原因になります。
まずはあたたかく見守る姿勢を持ちましょう。
塾・家庭教師で出す宿題あるある
塾、家庭教師で多いのは、先生から解き方を教えた。
でもちょっとだけ中身を変えた問題が解けない場合が多いんです。
基本に自信をつけていない場合、こういうことがよくあるんです。
先生は解説を渡した。
それでもわからなかったら解説を見ながら解いて、
そして自分で〇つけして、ノーヒントで解けるようになるまでノートに自分で解いて、自分で〇つけ。
それをノートに書いて残して持ってきて。
それが宿題です。
そういった宿題をやってこない生徒が、すごく多いんです。
ハードルが高いんですよ。
「解かせるだけ」の宿題は、意味がありません。
“できるようになるまで一緒にやる”👉できるようになったら宿題でたくさん解く
が、成績アップの秘訣です。
環境改善の具体策
- うるさい場合 → 静かな部屋に移動
- 勉強中に話しかけてしまう → 用事は休憩時間まで待つ
- 部屋が散らかっている → 一緒に片付ける
部屋が散らかっているは、あるあるです。
親が片付けなさいと言っても聞かないときは、一緒に片づけをしてあげましょう。
片付けは「親がやってあげる」より「一緒にやる」方が効果的です。
片付けのコツや工夫は、「こうしなさい」だと子どもは押し付けられた感を感じるだけなので、アイデアとして伝えましょう。
❌つい言ってしまうNGワードと✅子どもの力を伸ばす声かけ
❌「なんでこんなのもできないの?」
✅「どこで止まった?(語?式?段落?)—ここだけ一緒にほど解こう。
❌「早くやりなさい!」
✅「19:00から20分だけやろう。終わったらお茶にしよう🍵」
❌「間違ってる」
✅「ここまでは合ってる。この記号だけ直そう。」
質問メモで“放置”をなくす 📝
📝解説が読みにくい時は最初から質問でOK(読むことを強制しない)。
📝わからなかった問題のページ/番号/どこがわからないかをその場で書く。
問題を読んでもすぐには理解できないこと、ありますよね。
そんなとき、「この問題のここがわからない。」
と具体的に言えず、「コレ、わからない」と問題の番号を指さすことで精一杯なことがあります。
でも、それで大丈夫です。
自分で一生懸命考えてもどうしてもわからないことは、誰にでもあります。
だからこそ、そういうときの気持ちや「どこがわからないのか、わからない」ということも、メモしておきましょう。
忙しい日は「聞く」だけでも関わる
- 「今日はどこまでやった?」
- 「一番むずかしかった問題はどれ?」
- 勉強の中身より勉強をした事実を認める声かけが効果的です。